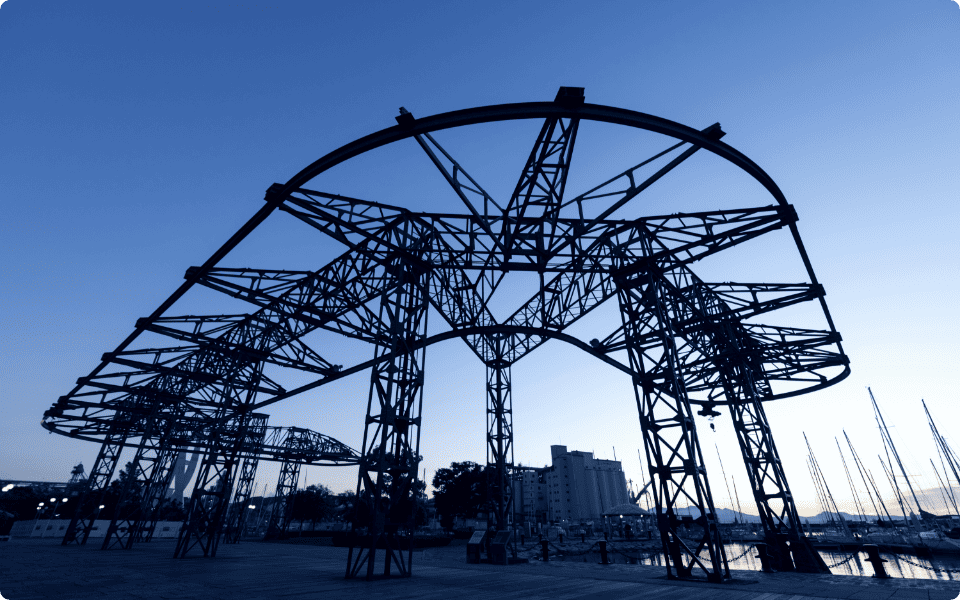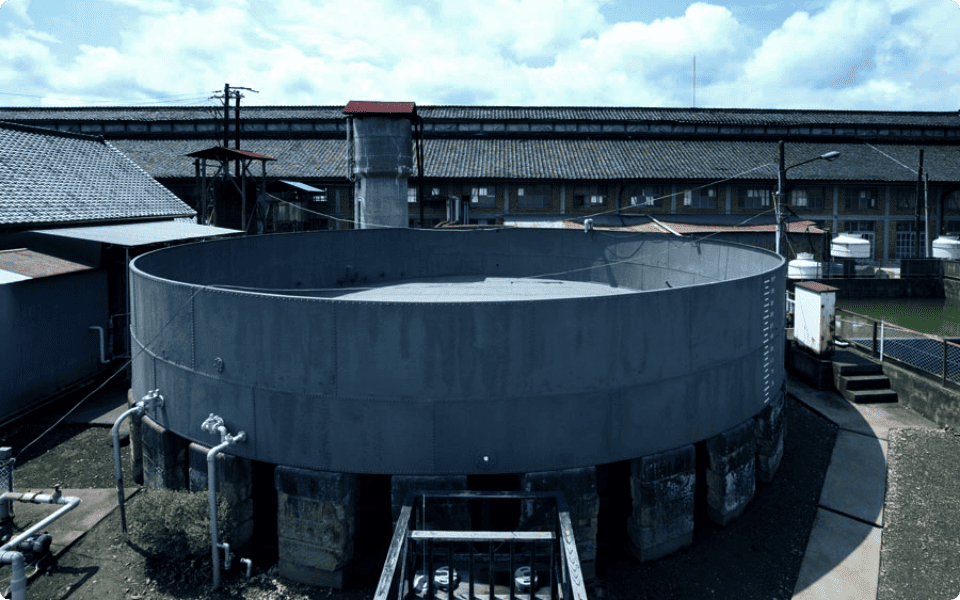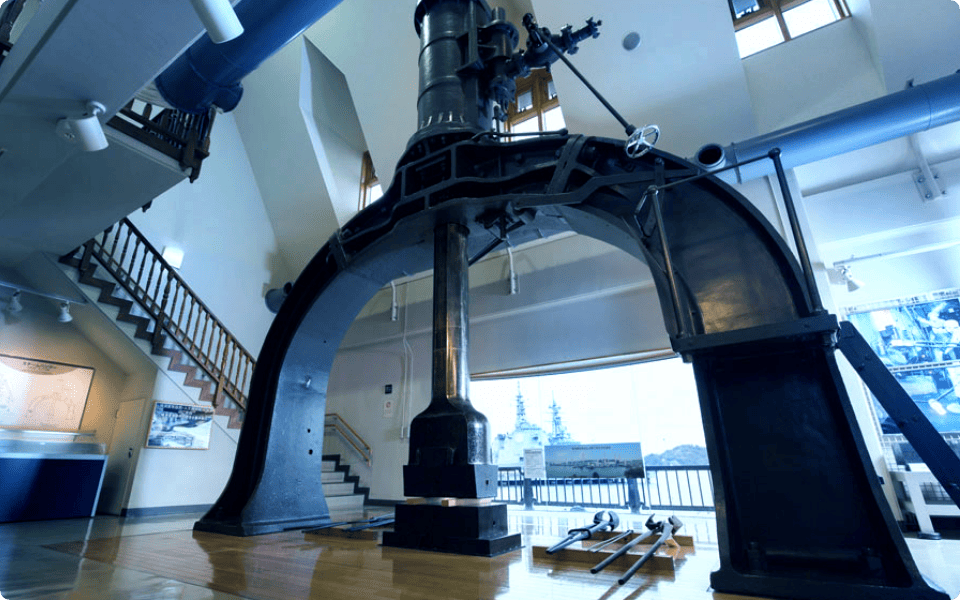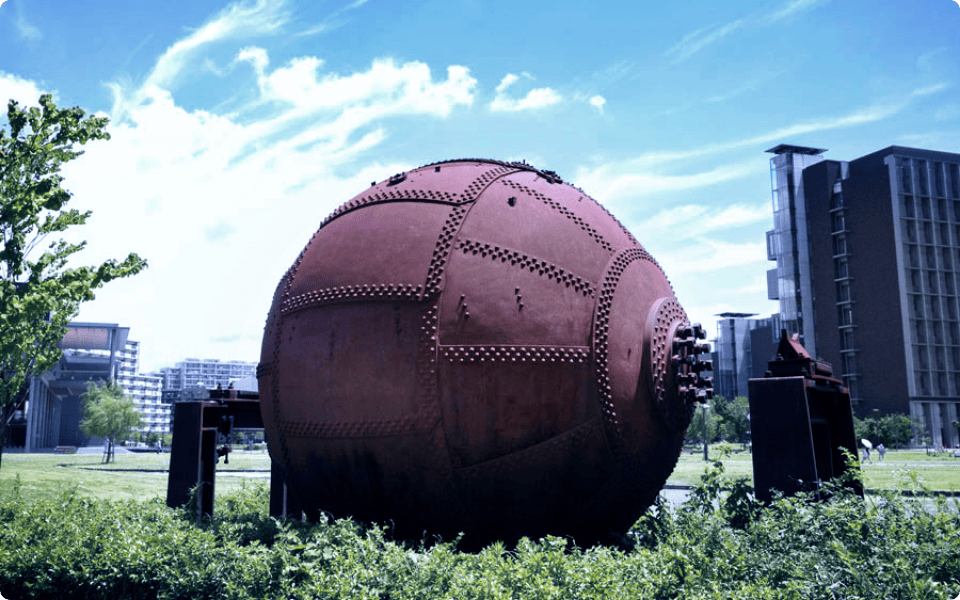東京打刃物

東京打刃物

足立
名だたる華道家が愛用する花鋏

東京打刃物。江戸時代の刀鍛冶をルーツとし、1871年(明治4年)の廃刀令を機に、多くの鍛冶師が包丁や鋏、大工道具など生活に必要な刃物づくりへ転業した伝統工芸である。打刃物の産地としては、岐阜県関市や兵庫県三木市などが有名だが、東京は少数精鋭でその道のプロのニーズに応えてきた。現在も数は少ないものの、足立区や台東区、荒川区などで伝統的な技法を守り続ける職人がいる。
いけばなや盆栽に使われる花鋏(はなばさみ)。日本の名だたる華道家から高く評価される『國治(くにはる)』ブランドを継承する川澄巌氏もその一人。厚生労働省の「現代の名工」にも選ばれた川澄氏は90歳になる今も足立区にある工房で、約80もの工程を一人でこなす。
川澄氏がつくる花鋏の特徴は、軽くて持ち疲れのしない抜群の使い心地とそのフォルムの美しさにある。メンテナンスを怠らなければ、百年は持つといわれる一生ものだ。父である先代の川澄国治氏に師事し、その背中を見て技術を学んできた。中でも鋏の切れ味を左右する仕上げの作業では、二本の刃の微妙なすき間を調整するため鋼より柔らかい錫や亜鉛の台の上で優しく触れるように叩く。まさに技の真骨頂だ。

「戦前、父は医療用の刃物から始めて一代で『國治』を世に広めた。『丸いものは丸く、平らなものは平らに』が口癖だった」。基本に忠実な先代の教えを守り、巌氏がその名を不動のものとした。
東京・日本橋にある老舗刃物店の木屋。1792年(寛政4年)創業の同社は包丁をはじめ、各種鋏や理美容品など様々な高級刃物を取り扱う。「『國治』の花鋏といえば、いけばなの世界では非常に名の知れた、日本最高峰のブランド。草月など各流派の家元クラスが愛用している」(企画総務部・石田克由さん)と話す。
「父はバイオリンや写真など多趣味な人だった。世界の一流のものを見て仕事に活かせと教えられた」と話す川澄氏。切れ味だけではない『國治』の機能美は豊かな感性によっても形づくられてきたのだ。
メタルワングループ広報誌 Value One Autumn 2022 No.78より