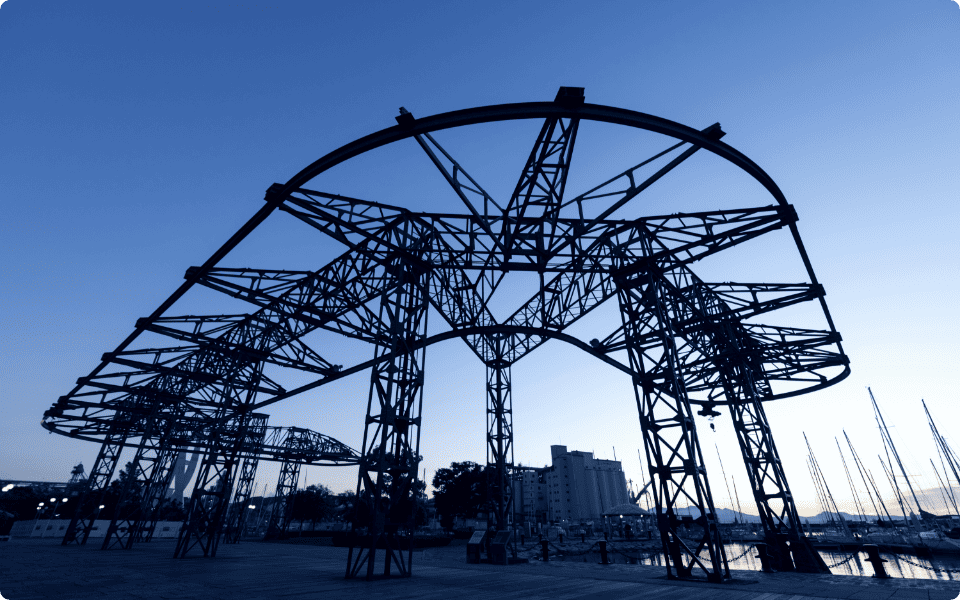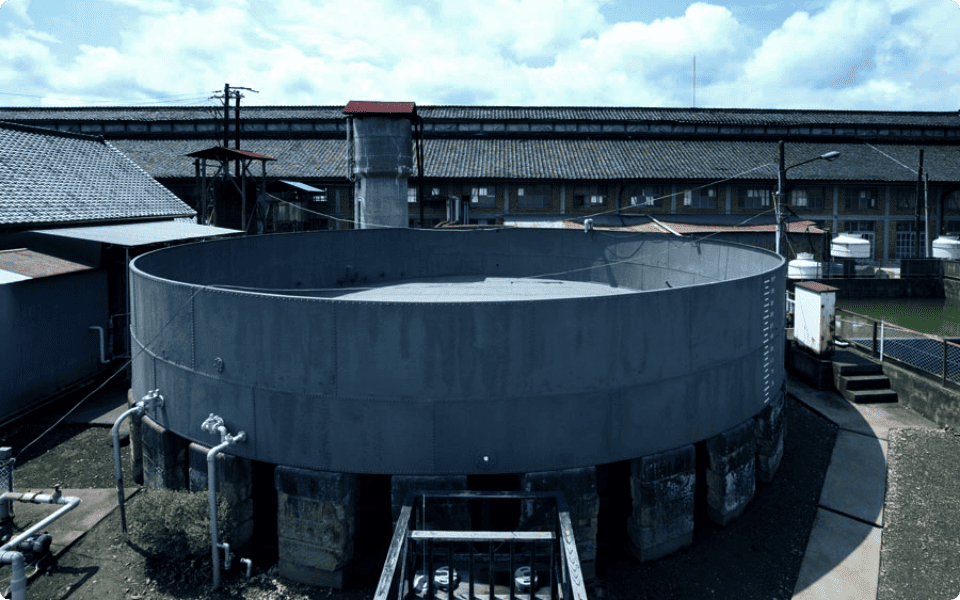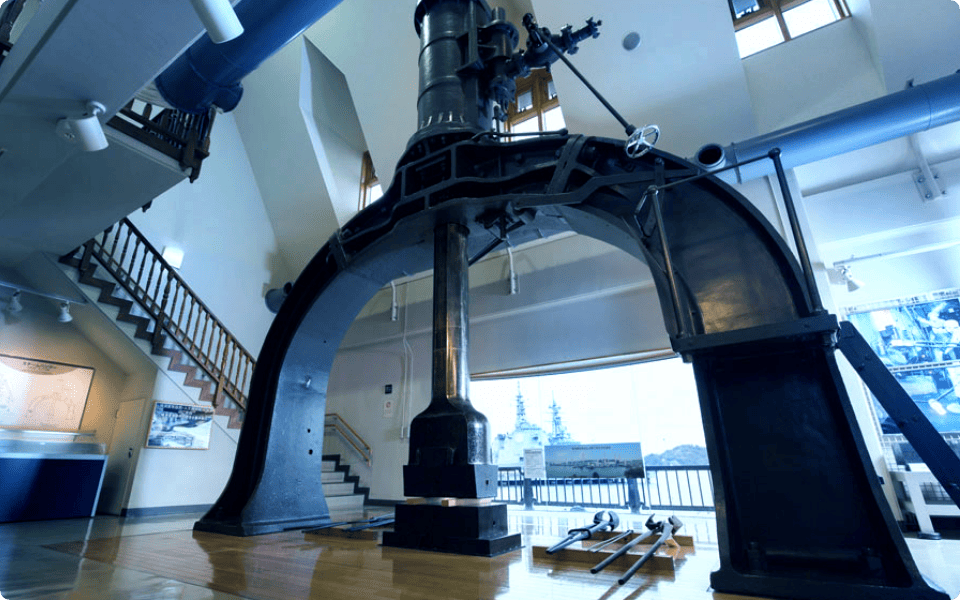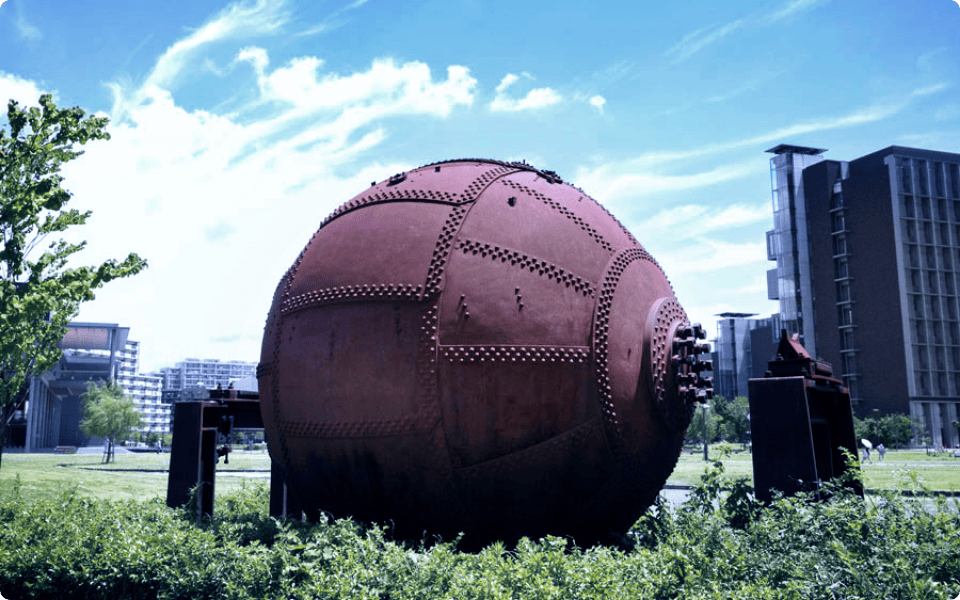五城目鍛冶

五城目鍛冶

秋田県五城目町
500年の伝統を誇る鍛冶を継承

かつて日本には、どこの町や村にも鍛冶屋があった。包丁や鋏など身の回りの道具から鎌や鍬、鉈といった農林具、狩猟用の山刀や漁具に至るまで鍛冶職人のつくる様々な鉄製品は庶民の暮らしに欠かせないものだった。日本の鍛冶の多くは古来より伝わる日本刀の鍛冶技術をルーツに、真っ赤に熱した鋼を繰り返し打つことで形を整え、粘り強く切れ味の鋭い刃に仕上げていく、優れたモノづくりの担い手だった。
しかし、高度成長期以降、安価な工業製品の普及や農林水産業の機械化、さらに地方の過疎化や後継者難が追い打ちをかけ、全国各地で鍛冶の伝統が途絶えていった。
-

「鍬や鎌は野鍛冶の基本」と語る布川氏
秋田県五城目町。約500年の歴史を誇る「五城目鍛冶」の産地として知られ、ここにもかつて数多くの鍛冶がいた。現在、ただ一人の鍛冶職人として伝統を受け継ぐ布川刃物製作所の布川滋氏。27歳の時に自動車メーカーを辞め、鍛冶の世界に飛び込んだ稀有な職人だ。自動車メーカーではデザイン部門にいたが、「最初から最後まで一人で責任を持ち、お客様に直接届ける仕事がしたい」と憧れだった鍛冶の道を志した。
縁あって五城目町の伝統工芸を育成する制度の第1期生となり、伝統工芸士の故小玉正太郎氏のもとで修業を積んだ。昔の徒弟制度のように雑事も何でもこなし、畑仕事も手伝う中で、実際に自分で鍬や鎌を使った経験が後に生きた。「使い手の要望をいかに汲み取れるか」。20年以上経った今も大事にする布川氏のモノづくりの原点である。

日本の鍛冶文化に詳しく、学生時代に五城目町で調査し、布川氏を知る北海道武蔵女子短期大学の齋藤貴之准教授は「鍛冶は日本の職人文化の象徴。その存続は確かに厳しいが、一方で“本物”を志向するニーズは高い。布川さんのようにデザインやネット販売など工夫次第で生き残るチャンスはある」と話す。
「五城目鍛冶の伝統を次世代に伝えることが自分の使命」と語る布川氏。地元の小中学生らを対象に工房見学を定期的に開催。かつての自分のような鍛冶に憧れる担い手の出現を待ち望んでいる。
メタルワングループ広報誌 Value One 2023 No.81より